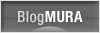1年目は時間もなかったので、記述のネタは学校の解答例をひたすら模写し、パターンとして刷り込む作業が主体でした。内容を考えるより、時間を短く端的に質問に回答する訓練しかする時間がなかったです。
2年目は半年間の準備期間があったのと、どんな課題がでるか定かではなかったので、幅を広げるためにも以下の2つの資料を参考資料として眺めてました。
限られた枚数で、計画内容を端的に伝えるためのプレゼン資料です。建築計画だけでなく、構造と設備についても少ない文章とイメージで審査員に伝えるための表現は、記述の試験においてとても参考になると思いました。
記述の回答をする際に、今までにない切り口や表現を会得することができます。といっても、結局時間優先でありきたりな回答になりますが、どんな問題がでても答えられるという心の持ちようが違ってきます。
内容は基本的内容から最新技術や傾向についても提案されているので、単純に建築の知識の蓄積としても役立つものだと思っています。
公開されているものは庁舎などが多いのですが、実際に建つ建物についてどのような計画がされているのか見ることができます。図面とその解説を見ることができるので、環境、設備計画、構造で、実際につくられる技術を知識として会得できるので、記述のネタになります。実務で大規模案件をやったことがない方でも、実際の設計でどのようなポイントが重要なのか見ることができるので、参考になるかと思います。
相変わらず試験と実務はかけ離れたものですが、ここ数年で少しだけ受験者の「提案」のアピールが採点の対象となってきたように思います。「提案」ありきでは、案はまとまらないので、試験と割り切る必要がありますが、「提案」がない回答は小さなミスひとつで他の案に負ける案になってしまうような気がします。
できるだけきれいなプランをつくってできる余白や図面表現に現れない部分に「提案」をぶち込むイメージです。
記述は、そんな「提案」を好き勝手できる側面があるので、実践的な知識があったほうがプラスになるかと思います。ただ単に単語を並べた文章は読んですぐわかりますので、一歩踏むこめる記述を書けるように準備することは大切だと思います。
上記2点の資料は、コンペやプロポの勝者が作成している資料でもあります。そういう意味でも洗練され役立つ内容がたくさんある参考資料かと思います。先にも書きましたが、実際の試験ではここで得た知識はほとんど披露できないまま終わりますので、無駄な勉強と言われるかもしれませんが、どんなポイントをアピールしたら良いのかといった基本的な部分でも、自分的には大いに参考になったと思っているので紹介しておきます。
にほんブログ村
人気ブログランキングへ