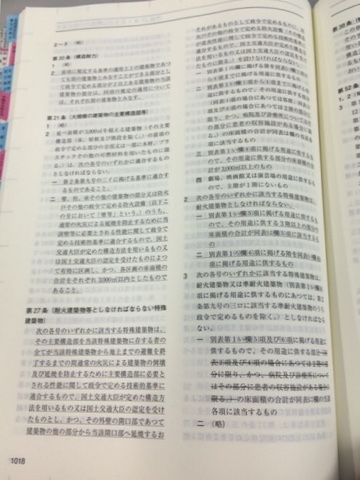|特定建築物の用途
12191
「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」において,保健所は,特定建築物に該当する.
⇒○
令4条だけぱっと見て判断しました。
危ないね、もう一度言葉の定義を確認しないと。
法2条17号に次のように記載。
「特定建築物のうち所定の条件を満たすものを特別特定建築物という.」
というわけで、特別特定建築物は、特定建築物の一部。
08194
「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」において,特定建築物には,賃貸住宅は含まれない.
⇒○
「バリアフリー新法2条第十六号」より,「特定建築物とは,多数の人が利用する政令で定める建築物をいう.」とわかる.その「政令」については,「バリアフリー新法(令)4条」にあり,問題文の「賃貸住宅」は,その「各号」のいずれにも該当しないため,「特定建築物」ではない.
賃貸住宅の定義ってなんだ?
共同住宅かもしれないし、一戸建てかもしれない。
令4条には、確かに書いてないけど、
そもそも分譲か賃貸かの区別が元々ないような。。。
深入りする必要はない。
賃貸住宅=一戸建てもあり得る ⇒ 特定建築物に含まれない。
(分譲住宅でも同じだな。。。)
そもそも条文に書いてないからOKという
模範解答を頭に入れることでいいかもしれない。
12194
「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」において,浴室は,建築物特定施設に該当する.
⇒○
浴室、シャワー室(あわせて浴室等)。
なぜわざわざ規則まで飛ばしてるのか。改定しろ!!
|既存や増築関連
19233
建築主等は,その所有し,管理し,又は占有する現に存する特別特定建築物について,建築物移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならない.
⇒○
特別特定建築物=移動等円滑化基準への適合義務
というのは間違い。
法14条1項は、
「新築」特別特定建築物=適合義務
5項には、
「既存」特別特定建築物=適合努力
(既存特別特定建築物という用語はないので注意)
24254
既存の特別特定建築物に,床面積の合計2,000㎡の増築をする場合において,道等から当該増築部分にある利用居室までの経路が1であり,当該経路を構成する出入口,廊下等の一部が既存建築物の部分にある場合には,建築物移動等円滑化基準における移動等円滑化経路の規定は,当該増築に係る部分に限り適用される.
⇒×
令22条に、増築等に関する適用範囲があり、
第一号 当該増築部分にかかる部分
第二号 道等から(略)出入口、廊下等、、、
と、適用範囲が6つ記載。
一号では増築等の部分とされているが、
その他いわゆる特定施設に係る部分は、
増築部か既存部は、規定されていない。
=既存部でも二号以降の部分に該当すれば、適用範囲内
|その他
22284
「建築物移動等円滑化誘導基準」においては,多数の者が利用する主たる階段は,回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難であるときは,回り階段とすることができる.
⇒×
円滑化誘導基準か、円滑化基準かを見落とすと致命傷の問題。
誘導基準の方が、より厳しい基準なので、回り階段に関する緩和はなし。(省令4条)
一方の円滑化基準は、回り階段しか設置できない場合は、それでOKと緩和規定あり。(令12条六号)