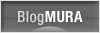家のPC更新に便乗して、windowsタブレットを新年に購入。
家用といいつつ、勉強専用として夏の終わりまで使うことに。
購入したのは、こちら。
Acer Aspire Switch 10。


オフィスソフトもほしかったので、プリインストールされたタイプを選択。
それでも4万を切る値段(購入当時)で購入でき、いい買い物ができたのではないだろうか。
オフィスなしであれば、更に安いし、ほかの機種も候補にするとそこまでの出費にはならない。
持ち運びを考慮すると8インチタイプも候補になる。(解像度的には問題なし。)
しかし、画面の大きさを実機で確認して、小さいと判断。
10インチ以上の画面を必須条件とした。
ウルトラブック系も候補となったが、携帯性を重視してタブレット型に。
(実際は、どっちも可能な2in1を選択)
OSは、windows8.1。当然タッチパネルでの操作となる。
タブレットといっても中身はwindowsマシンなので、合格物語も問題なく動作。
重たいデータを扱うわけではないので、このぐらいの低スペックでもサクサク動く。
2in1なので、家にいるときや図書館といった場所では、ノートPCとして利用でき、
通勤時は、タブレットとして使用し、どこでも好きな形態で合格物語を利用できる。
といっても今のところ、10インチある画面を満員電車のなかで取り出して見るということに
慣れてなく、車内のスペース的にも厳しいので、結局移動中は、スマホ頼り。
片手でしっかりホールドできるケースがほしいところ。
合格物語をタッチパネルで操作することについては、相性はよいと感じている。
ボタン風な操作画面なので、タッチパネルでも充分ストレスなく操作可能。
一点だけ不満があるとすると、マーカー機能が使いにくい(使えない)ことぐらいか。
100均でちょうどよい保護ケースがあったので、そこにタブレットとルーズリーフを入れて、
問題をすすめながら、重要点等をルーズリーフに書き出すようにしている。
タッチパネルなので、デスクトップ上の付箋に手書きができるので、
とっさのメモ程度ならPCの画面上に手書き入力ができるのが新たな発見。
という感じで、多少の出費だったが(最終的に家に還元するので余分な出費ではないと主張中)、
勉強環境はすこぶる快調。
あとは、やる気と記憶力がついてくるか。。。